「そろそろ親の家、何かしないと危ない気がするんだよね…」
離れて暮らす高齢の親のことを思い浮かべたとき、
ふとそんな不安がよぎる瞬間が増えてきた方へ。
転倒は高齢者にとって命に関わることもある重大なリスクです。
でも、「まだ元気そうだし」「嫌がられたら困るし」と
つい様子を見るだけで終わってしまう──そんな気持ちもよく分かります。
だからこそ今回は、
作業療法士として高齢者の転倒予防に関わってきた立場から、
まず整えてほしい“住まいの3カ所”を厳選してお伝えします。
大がかりなリフォームではありません。
手すりひとつ、照明ひとつでも、「転ばせない環境」はつくれます。
親を思うあなたの気持ちが、具体的な行動につながるように。
現場で見てきたリアルな視点で、やさしく解説していきます。
最初に整えたい場所は「玄関」です。
「出かける」ときも「帰ってくる」ときも、
必ず通るこの場所は、高齢になると“危ない動き”がたくさん潜んでいます。
特に注意したいのが、
✔ 靴を履いたり脱いだりする中腰姿勢
✔ 段差をまたぐ動作(昇り降り)
✔ ドアの開け閉めと同時にバランスを取る動き
ほんのわずかなつまずきが、
転倒や骨折、そしてその後の寝たきりにつながるケースも珍しくありません。

■ 導入におすすめの対策
- 据え置き型の手すり
→ 工事不要。置くだけで昇降時の支えに。嫌がられにくく設置もしやすい - 玄関マットや段差解消ステップ
→ 小さな段差をなだらかに、足の引っかかりを減らす - 照明の明るさを見直す
→ 夕方以降は影になりやすく、明暗の差でつまずきやすい
「まだ大丈夫そう」な今のうちに、小さなサポートを加えておくことで
“転ばせない環境”を無理なく作ることができます。
2つ目に整えておきたいのが「トイレ」。
一見コンパクトで安全そうに思えますが、
実は“立つ・座る・向きを変える”といった動作が集中する、
高齢者にとっては非常にリスクの高い場所です。
たとえばこんな場面を想像してみてください。
──夜中に目が覚め、足元がおぼつかないままトイレへ。
便座に座るときにグラッと傾き、
あわててタンクや壁に手を伸ばす……。
そんな“あと一歩”のところで、
実際に転倒してしまった方を何人か聞いています。
高齢になると、立ち座りに必要な太ももの筋力や
バランスを保つ能力が低下します。
特に夜間は体が冷えていたり、血圧の変動や寝不足などでふらつきやすく、
「普段できている動作」こそが危険になるのです。
■ こんな工夫をしてみましょう
- 据え置きタイプのトイレ手すり
→ 腰を下ろす・立ち上がるときに“しっかりつかめる場所”があるだけで安定感が大きく変わります。
→ 工事不要なので、設置のハードルも低く、プレゼントとしても◎。 - 便座を高くする“補高便座”
→ 立ち上がり時の角度がゆるやかになり、力を入れすぎずに動けます。 - 足元にセンサー付きライトを
→ 夜中に目が覚めて、薄暗い廊下やトイレへ向かうとき、
足元が自動で照らされるだけで、転倒リスクは格段に下がります。
ほんの少しの工夫で、
“事故になりやすい場所”を“安心して使える場所”に変えることができるのがトイレ。
誰にも気づかれずに起きがちな「家庭内の転倒」を防ぐためにも、
まずはここから整えてみてください。
転倒リスクが高い場所と聞いて、
トイレや浴室など“動作の多い場所”を思い浮かべる方は多いかもしれません。

ですが、実は転倒事故が多いのは──
「何もない」廊下や部屋の移動中だったりもします。
たとえばこんな場面を想像してみてください。
──朝、寝室から廊下に出て、キッチンへ向かう母。
まだ目も覚めきらず、照明もつけずに歩き出し、
ふとした足のもつれで足元がふらつく。
「とっさにつかまる場所がなかったんです」
そう語るご家族は少なくありません。
若い頃は無意識にできていた歩行や方向転換も、
年齢とともにバランス感覚や筋力が低下し、
ちょっとした段差やスリッパのズレで転んでしまうのです。
■ 廊下や居室の動線を整えるポイント
- 手すりを「つける」よりも「つかまれる場所をつくる」意識で
→ 廊下に手すりをつけるのが理想ですが、
工事が難しい場合は、家具の位置や壁際の補助手すりを活用する方法もあります。 - 足元照明・人感センサー付きライトの設置
→ 特に夜間や早朝の移動では、足元の明るさが安全に直結します。
コンセント型のライトや、置くだけのセンサーライトもおすすめです。 - コードや敷物を整理し、床を“見える状態”に保つ
→ 電気コード、ずれたカーペット、新聞紙──
それらは高齢者にとって「見えない障害物」です。
転倒は、準備ができていない“何気ない一歩”で起こります。
だからこそ、意識して整えることで大きな事故を防げるのが、
この「廊下・居室の移動動線」なのです。
私はこれまで、作業療法士として多くの方の「転倒後」に立ち会ってきました。
──ほんの数センチの段差で足をとられ、転んでしまった
──トイレで立ち上がろうとしたとき、つかまる場所がなかった
──夜中の移動でふらつき、玄関の段差に足をぶつけた
倒れてしまった方も、ご家族も、口を揃えて言います。
「わかってたんです。本当は先に片付ければよかった…」
「手すりをつけようか迷っていたのに、つい後回しにしてしまって」
その言葉を何度も聞いてきました。
転倒は、その瞬間だけの出来事ではありません。
骨折すれば、入院・手術・リハビリ……と続きます。
その間に筋力や体力は落ち、
「もう歩くこと」さえ叶わなくなる方もいます。
それだけではありません。
転んだことによって、「外に出るのが怖くなった」
「自信がなくなって何もやりたがらない」と
生活の質そのものが変わってしまうケースも少なくないのです。
だからこそ私は、
「まだ元気な今からでも、家の中を整える価値がある」と強く思っています。
もちろん怪我してしまった後でも整備する意味は大いにあります。
手すりを置く
照明を足元に増やす
滑り止めマットを敷く
たったそれだけのことで、
“転ばなかった未来”をつくれるかもしれない。
整備したからといって、100%転ばないわけではありません。
でも、転倒の可能性を確実に減らすことはできる。
そしてそれは、高齢の親の“健康資産”を守る行動であり、
あなた自身の「もしものときに後悔しないための準備」でもあります。
私は、住環境の整備や福祉用具の導入を、
単なる“便利グッズ”ではなく、
家族の暮らしと気持ちを支える道具のひとつとして伝えたいです。
たとえ小さな一歩でも、
その工夫が、転ばせない・後悔しない未来につながることを、
どうか知っておいてほしいのです。
転倒は一瞬。
でも、その一瞬が、高齢の親の生活を大きく変えてしまうことがあります。
歩けなくなる
外に出られなくなる
自信をなくして、笑顔が減ってしまう
そうした“もしもの未来”を少しでも遠ざけるために、
できることがあります。
それは、大がかりなリフォームではありません。
置くだけの手すり、明かりの工夫、滑りにくい床マット……
ちいさな備えでも、暮らしの安心感は大きく変わります。
整えるということは、
「何かあってからでは遅い」と感じている、
あなたの“やさしさ”をかたちにする行動です。
そしてそれは、
親の自立を支えることでもあり、
あなた自身が「してあげられた」と思えるための準備でもあります。
どうか、“転ばない暮らし”のために、
できるところから、ひとつずつ整えてみてください。
その一歩は、家族の未来を守る力になります。
「まずはどこから?」という方には、転倒リスクが高い玄関まわりから整えるのがおすすめです。以下のようなアイテムがその第一歩になるかもしれません。
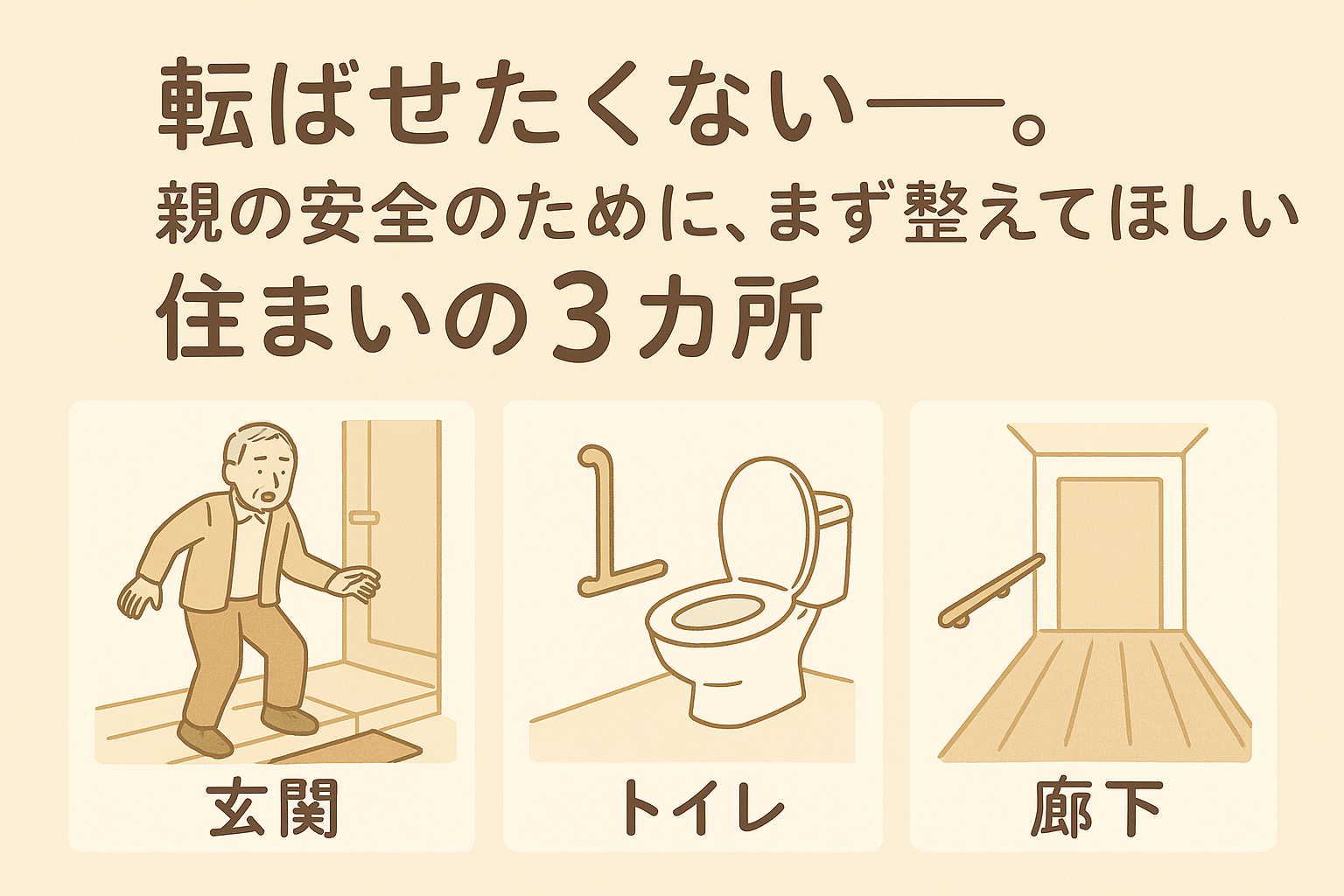
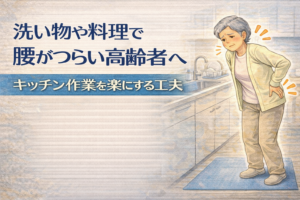
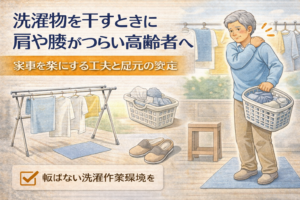






コメント