はじめに|「ほんの数センチ」で転ぶことがあります
「マットの端に引っかかって転びそうになった」
「部屋の切り替えでちょっとした段差がある」
「こたつのコードに足を取られて転びそうになった」
こうした“ほんの小さな段差や引っかかり”が、高齢者にとっては大きな転倒リスクになることがあります。
私はリハビリの現場で、“段差につまずいた”ことがきっかけで骨折や入院につながった方をたくさん見てきました。
今回は、わずかな段差や引っかかりに気づき、予防するための視点をお伝えします。
1|段差でつまずくのは「足が上がっていない」から?
年齢とともに、以下のような変化が起こりやすくなります:
- 歩幅が狭くなり、足を前に出す動きが小さくなる
- つま先を上げる動きが弱くなる(足首の背屈制限)
- 足を「上げたつもり」でも、ほんの数センチ足りない
その結果、敷居やカーペットの端、畳とフローリングの境目などで“つまずく”ことが増えてきます。
2|視界や認知の変化で「段差に気づけない」
足の動きだけでなく、見えていない・気づいていないこともつまずきの原因になります。
- 段差やマットの端が床と同じ色で見分けにくい
- 和室と洋室の切り替えが“段差”として認識されていない
- 注意力が散漫で、足元に意識が向いていない
とくに認知機能や視覚機能に変化があると、環境の変化に気づくのが遅れ、転倒しやすくなります。
3|“転びやすい場所”は家の中にたくさんある
以下のような場所が、実は危険ポイントになっていることがあります:
- 敷居が5〜15mmだけ高くなっている
- マットの端が浮いている or めくれかけている
- カーペットが波打って足に引っかかる
- 部屋の切り替えで床材の厚みに段差がある
- 床に這っているコード(こたつ・延長・掃除機など)に足を取られる
私の経験上、**特に多いのが「コード類への引っかかり」**です。
こたつコードや延長コードは細く、視認しにくいため、**高齢者にとっては“見えていない障害物”**になってしまいます。
4|つまずきを防ぐための環境の工夫
✅ 段差がある場所は、テープやシールで視覚的に色をつける
✅ 敷居やマットの高さが合わない場合は、低くする・固定する・撤去する
✅ 踏み込む場所が波打っているなら、フラットな床材に張り替える
✅ コード類は壁際に沿わせる・カバーでまとめる・床を這わせない
✅ 頻繁につまずく場所は、手すりや“支えられる場所”を近くに置く
特別な器具がなくても、身近な材料でできる工夫がたくさんあります。
まとめ|「段差=危険」と気づくことがスタート
転倒は、特別なときではなく「いつもの生活の中」で起きます。
✅ 足が上がりづらい
✅ 段差が見えづらい
✅ つかまる場所がない
✅ コードが足に引っかかる
こうした条件が重なると、ほんの数センチの差でも転倒してしまいます。
まずは、“家の中の小さなつまずき”に気づき、その場所を一つずつ整えていくことから始めてみてください。
次回予告|身体機能を整えるセルフケアへ!
次回からは、「身体機能そのもの」を整えて、転ばない体づくりに役立つセルフケアや運動の工夫をご紹介していきます。







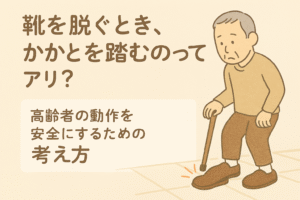

コメント