「片付けたいけど、できない」の本当の理由とは?
高齢の親と暮らす、あるいは久しぶりに実家に帰ったとき
「なんでこんなにモノが多いんだろう」「片付ければいいのに…」
そう感じた経験はありませんか?
でも実は、**片付けないのではなく、“片付けられない”**のです。
高齢の方が整理整頓に手を出せなくなってしまう背景には、単なる体力や気力の問題だけではなく、「判断に伴うストレス」や「思い出への葛藤」があります。
捨てるか残すか、その判断が心をすり減らす
片付けとは、**“選択の連続”**です。
- これはまだ使える?
- 誰かにあげるべき?
- 思い出の品だけどどうしよう…
高齢になると、この一つ一つの判断がとても重く感じるようになります。
過去の記憶や家族との思い出が詰まった品ほど、**「捨てたら消えてしまう気がする」**と感じる方も多いのです。
また「何が必要か」という基準が年齢とともに曖昧になっていくことで、**“決めること自体が苦痛”**になることも少なくありません。
よくある実例|本当は片付けたいけれど…
- 昔の書類や写真を前にして手が止まる
- 衣類やタオルが大量にあるが、捨てるのが忍びない
- 「子どもに迷惑をかけたくない」と言いながら一人で抱え込む
実際、私が関わった方の中にも「本当は片付けてすっきりしたい」と口にされる方が多くいました。
でも、「どう始めていいかわからない」「判断がつかない」「誰かに任せてしまうのも不安」…という**行動に移せない“壁”**があるのです。
家族ができるサポート|“片付けさせる”ではなく“整える時間を共有する”
家族としては、無理に捨てさせたり、業者に一任してしまいたくなる気持ちもあるかもしれません。
でも、気持ちを置き去りにした片付けは、心の負担となり、かえって不信感を生むことも。
そこでおすすめしたいのが、“一緒に整える”という関わり方です。
実践的なサポート例
- 一緒に見ながら思い出を共有する
写真や手紙などは、話題のきっかけに。「このときどうだった?」と聞くだけで、気持ちの整理がつくことも。 - “今の生活に必要なもの”を優先に考える
過去ではなく“これから安全に暮らす”視点で。床にある荷物や使わない家具などは、転倒リスクの元になることも。 - 片付けの専門家や地域サポートを使う選択肢も
たとえば、地域によっては「シルバー人材センター」「生活支援サービス」「訪問型の福祉整理」なども利用可能です。
※筆者の地域(茨城県つくば市)では、要支援・要介護の認定がなくても利用できる高齢者向けの片付け支援サービスが存在します。
まとめ|片付けの目的は“安全で穏やかな暮らし”を守ること
モノを減らすことがゴールではありません。
大切なのは、**「安心して生活できる環境」**を一緒に整えること。
その過程に寄り添い、「捨てる」ではなく「整える」時間を共有する姿勢が、最も信頼されるサポートです。
次の帰省時や通話の中で、「どこか一緒に見直してみようか」と一言添えるだけでも、きっと一歩が踏み出せるはずです。
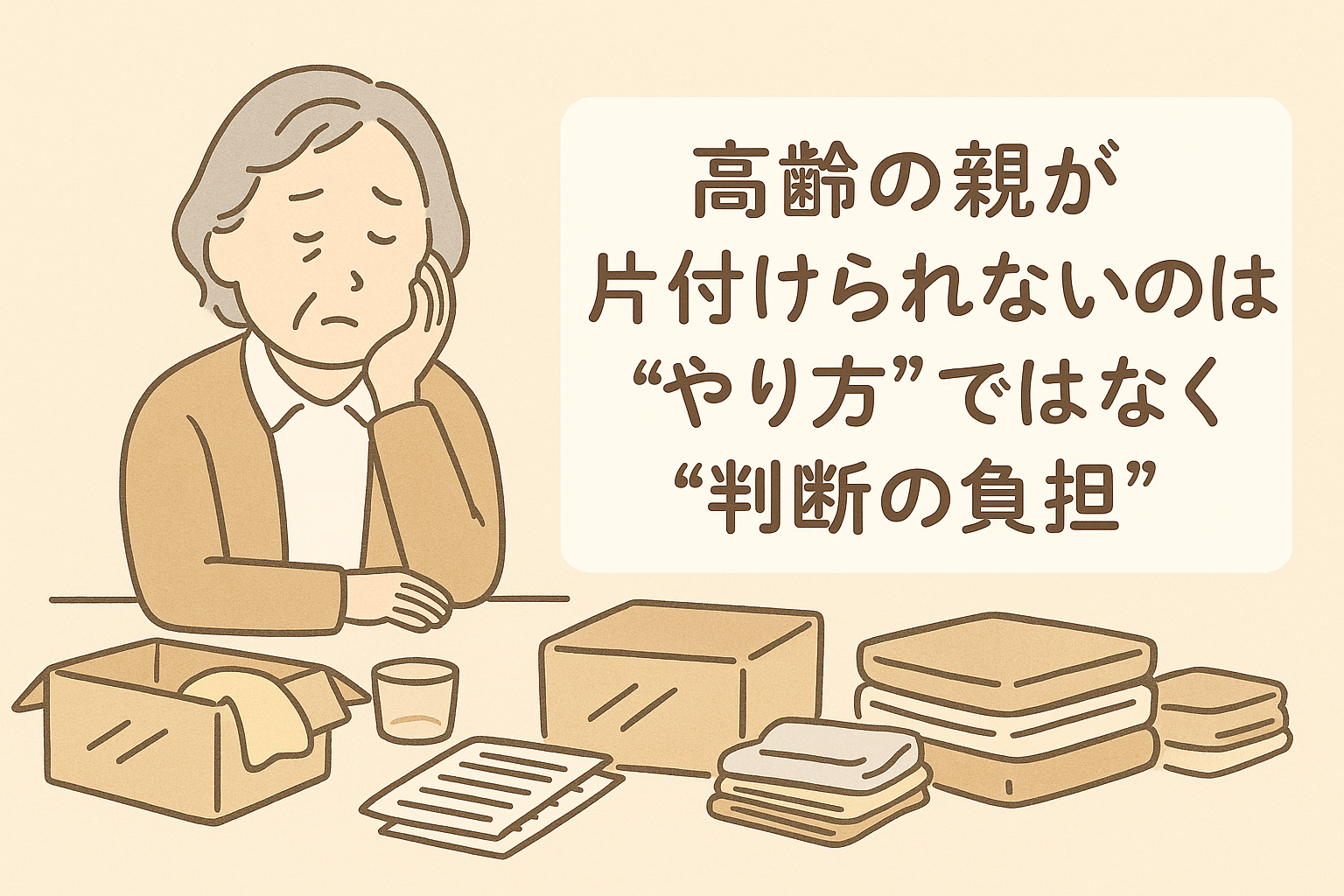
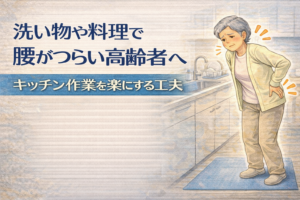
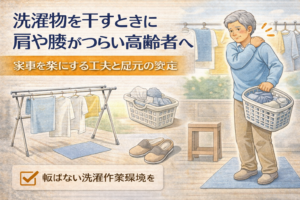






コメント