高齢者は暑さや寒さを感じにくくなり、体温調節もうまくできないことがあります。本記事ではその理由と、日常でできる温度管理の工夫をわかりやすく解説します。
【はじめに】
高齢者が「暑くないよ」「寒くないよ」と言っているのに、熱中症や低体温症になってしまう——
そんなケース、身近にありませんか?
実は、年齢を重ねると体温の感じ方そのものが変化してきます。これは「気のせい」ではなく、体の仕組みそのものが関係しているんです。
この記事では、
- 高齢者が温度を感じにくくなる理由
- 危険な温度トラブルの実例
- 家庭でできる温度管理の工夫
について、具体的にお伝えしていきます。

【1】高齢者が暑さ・寒さを感じにくくなるのはなぜ?
年齢を重ねると、
- 皮膚の感覚が鈍くなる
- 発汗機能が低下する
- 筋肉量が減って熱が生み出しにくくなる
- 自律神経の反応が遅くなる
といった変化が起こります。これにより、体の外の温度に対する反応が鈍くなり、自分の体温が上がっていても気づきにくい状態になります。
【2】実際に起こる温度トラブルの例
私が病院勤務時代に経験した中でも、こんなケースがありました。
- 「暑くない」と言っていた高齢の方が、室内で熱中症になって搬送された
- 寝室が寒すぎて、朝起きたら低体温になっていた
- 冬でも暖房をつけずに生活していて、足元から冷えをため込んでいた
どれも「本人の感覚」では問題なかったのですが、実際の室温は危険レベルでした。
【3】家庭でできる温度管理の工夫
高齢の方の健康を守るために、感覚に頼らず「見える化」することが大切です。
おすすめの工夫は以下の通りです。
- 温湿度計の設置(SWITCHBOTなど):快適温度・湿度が一目でわかる
- 室温チェックを習慣に:朝・昼・夜と1日3回確認する
- 足元の冷えに注意:カーペットやスリッパで底冷えを防ぐ
- 就寝時の温度にも配慮:エアコンのタイマー+毛布の使い方で調整
- 断熱シートやすきま風対策グッズの活用も◎
【4】デジタル温湿度計なら自動で記録・通知もできる
特におすすめしたいのが、SWITCHBOTの温湿度計です。
- アプリと連携できてスマホで確認可能
- 異常な温度・湿度になったらアラートが届く
- 記録が残るので、体調の変化と結びつけやすい
例えば「昨日より室温が高かったから頭がボーッとしていたのかも」など、振り返りにも使えます。
▶︎ おすすめ商品:
リンク
【まとめ】
高齢者は、体の機能の変化により暑さ寒さを感じにくくなっているため、「本人の感覚に任せておけば安心」というわけにはいきません。
家族や周囲の人が、数値で確認できる仕組みを取り入れることで、温度トラブルを未然に防ぐことができます。
室温・湿度の「見える化」、ぜひ始めてみてくださいね。

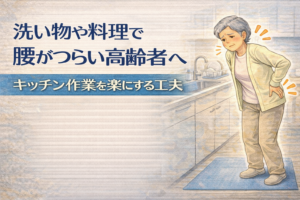
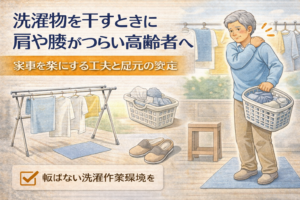






コメント